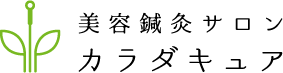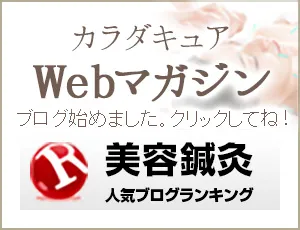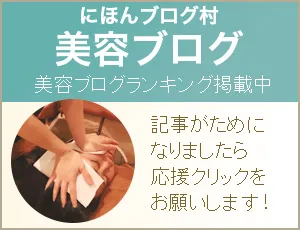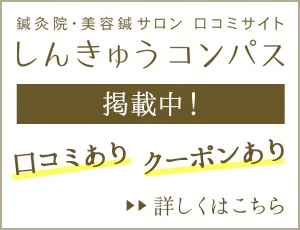ストレスが溜まると甘いものを食べてしまう、運動後に酸味のあるものが欲しくなるなどの経験はありませんか?
今回はそんな、なぜかこれ食べたいという無意識にも思える味覚の欲求についてお話ししていきます。
食べ過ぎることは良くありませんが、適量摂取することは、体にとっての助けにもなります。
「これ食べたい」はなぜ起きるのか、東洋医学的な視点からも交えてお話ししていきますので、自分の食生活をぜひ見直しながらご覧ください。
実は食べたくなる理由はこれかも!?
酸っぱいものが食べたい
疲労が溜まっている可能性が高いです。
クエン酸回路(エネルギーを生み出している仕組み)がうまく機能していない、疲労物質が溜まっている状態と考えられます。
クエン酸(梅干し、柑橘系など)を摂取するのがオススメですが、それでも酸っぱいものが食べたい時はビタミンB群の不足も考えられるので、豚肉、レバー、アーモンド、玄米などの摂取がオススメです!
東洋医学的には、酸味は「肝」と関係します。
甘いものが食べたい
エネルギー元となる3大栄養素(炭水化物、タンパク質、脂質)のいずれかが不足している、ストレス、ホルモンバランスが乱れていることが原因の可能性があります。
エネルギー補給の際は、菓子パンなどで血糖値が急激に上がらないよう(血糖値スパイク)に気をつけましょう。→https://www.karadacure.com/blog/id=9421
チョコレートが食べたい時は、マグネシウム不足も関係している可能性がありますので、マグネシウムを一緒に摂るのがオススメです。
東洋医学的には甘味は「脾」と関係します。
しょっぱいものが食べたい
ミネラル不足が考えられます。
特に運動後、飲酒後はミネラルが不足する(体内のアルカリ度を調整ができない)ことでしょっぱいものが食べたくなります。
過剰に塩分摂取しないように気をつけながら、カリウム、鉄分、マグネシウムなどを摂取するのがオススメです。
東洋医学的には塩辛いようなしょっぱいものは「腎」と関係します。
辛いものが食べたい時
ナトリウムやミネラルが不足し欲していることが考えられます。
他にも、イライラが溜まっている時の発散のため、食欲がないときに刺激で食欲回復したいため、脳内ホルモンの影響で辛さがクセになり(快感を求める)刺激を欲してるため、なども辛いものが食べたくなることに関係すると言われています。
東洋医学的には辛いものは「肺」と関係します。
苦み
苦味のあるゴーヤなどはポリフェノールやフラボノイド、カロテノイドなどが含まれ、抗酸化、抗炎症、活性酸素除去などに役立ちます。
このような作用を欲している場合や、消化器、心身のバランスを整えたい時に食べたくなることがあります。
苦味が欲しいときは、マグネシウム、鉄分、ビタミンB群、抗酸化成分が取れているかと栄養バランスを見直し摂取してあげましょう。
東洋医学的には、苦味は「心」と関係します。
心は生命力そのものであり、弱くなる=死とも考えられるのと、心包につつまれている(守られている)ため基本的には弱ることはないです。
ですので、苦いものを無性に食べたくなることは他と比べると少ないかと思います。
五臓(臓器)と五味(味覚)
関連するそれぞれの五臓(臓器)と五味(味覚)は助ける働きがあります。
この五行論の関係性はコチラをご覧ください。
【東洋医学初級編~三大理論と五臓の変調~】
酸(すっぱい)は肝を、
苦(にがい)は心を
甘(甘い)は脾を、
辛(辛い)は肺を
鹵(塩辛い、しょっぱい)は腎を
補う作用があるとされます。
補う力もありますが、食べ過ぎると逆に臓腑を傷つける方に影響しますので、食べ過ぎには注意しつつ、適量取り入れるようにしましょう。
ここまで不足している可能性として栄養素を出しましたが、実際に何を食べたら良いかわからないという方はコチラもご参考ください。
美肌の作り方~食べ物編~
まとめ
様々な原因により、五臓六腑が弱っていたりバランスが崩れてしまうと、不調な症状として現れます。
痛みならわかりやすいですが、なんとなく食欲が止まらない…のような症状としてお身体がサインを出すこともあります。
日によって変わる自分の体調があまりわからないという方は、ぜひ定期的なメンテナンスをなさってみてください。
鍼灸師は、脈診や腹診、舌診などで五臓六腑の状態を診て、ご自身では気付きにくい状態、症状が出る前(未病)を見ることが得意です。
同じ鍼灸院で定期的に治療することで、より体調の変化も把握できて効果も出やすくなるため、オススメです。
ここまで読んでくださりありがとうございます。
この機会に栄養バランスの見直しと、「我慢できるから、症状が出てから、辛くなってから」ではなく、ぜひ定期的にケアしてお体をいたわってあげましょう!
美容鍼灸サロン カラダキュアの詳しいご案内はこちらからどうぞ