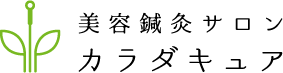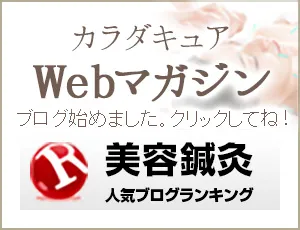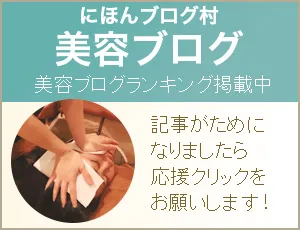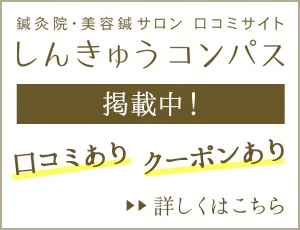ミネラルってなに?
ミネラルは、体を構成する主な元素(酸素、炭素、水素、窒素)以外の元素のことです。
体内で合成されないため、食事から摂取する必要があります。
人体に必要とされているのは「必須ミネラル」と呼ばれる16種類のミネラルで、その中でも1日の必要量により「多量ミネラル(7種類)」と「微量ミネラル(9種類)」に分けられます。
必須ミネラルは、体の成長、健康維持に関わり、機能や組織、心身のバランスを正常に保つなどの働きがあります。
様々なミネラルの働きによって生命活動が維持されているので、バランスよくとることが重要です。
ミネラルの主な働きと多く含む食材
多量ミネラル
カルシウム(体内ミネラルの中で1番多い)
→重要なのは、細胞外10000:1細胞内の割合で存在し保たれること。
【血清カルシウム(血液に含まれる)】
・神経や筋肉の興奮抑制
・血液凝固
・骨石灰化の促進
【骨カルシウム】
・骨や歯を形成
・血清カルシウム濃度維持、貯蔵
【細胞内カルシウム】
・神経伝達物質生成、ホルモン分泌(イライラ抑制など神経の安定)
・筋肉の収縮
・細胞機能調整(増殖、分化、形態の維持)
〈干しエビ、乳製品、小松菜、モロヘイヤなどに多い〉
リン(2番目に多い)
・エネルギー産生(ATP形成)
・浸透圧やpHバランスの維持
・骨や歯を形成
〈かたくちいわし、シラス干し、ベーキングパウダー、米ぬか、ハムなどに多い〉
カリウム
・利尿作用、血圧上昇を抑える
・浸透圧の維持
・筋肉の収縮
〈スルメ、アボカド、バナナ、わかめ、昆布などに多い〉
硫黄
・たんぱく質合成(皮膚、爪、軟骨、骨、腱、髪の毛などの形成)
・糖質、脂質の代謝(有害ミネラルの蓄積を防ぐ)
〈玉ねぎ、ニラ、ニンニクなどに多い〉
塩素
・胃液(胃酸)の構成成分(殺菌効果、浸透圧の維持)
〈食塩、醬油、漬物などに多い〉
ナトリウム
・血圧調整(過剰摂取→高血圧注意)
・体液の濃度調整(浸透圧の維持)
・筋肉の収縮
〈塩、みそ、練り物類、加工肉などに多い〉
マグネシウム
・骨や歯の形成
・酵素の働きを助ける
・神経伝達物質生成、筋肉や神経の興奮抑制
・血圧を下げる
✩不足すると→疲労感、筋肉のけいれん、足がつりやすい、寝付きが悪い、チョコが食べたくなることも!
〈あおさ、わかめ、ひじき、ほうれん草、玄米、アーモンドなどに多い〉
微量ミネラル
鉄
・赤血球(ヘモグロビン)の構成成分→全身の細胞に酸素を運ぶ
・筋肉内のミオグロビンの構成成分→血液中の酸素を受け取り、貯蔵
・酵素の構成成分(エネルギー代謝)
・神経伝達物質生成
〈レバー、赤身肉、かたくちいわしなどに多い〉
亜鉛
・発育、成長を促進(生殖機能、妊娠の維持など)
・新陳代謝の補助(ケガの回復、皮膚や髪の毛の健康を保つ)
・味覚を維持(視覚の正常化も)
・酵素の構成成分(免疫力向上、活性酸素除去)
・インスリンの構成成分(糖尿病を防ぐ)
・神経伝達物質生成
〈牡蠣、貝類、小麦などに多い〉
銅
・ヘモグロビンの合成補助
・酵素の構成成分(免疫力向上、動脈硬化予防、活性酸素除去)
・骨や血管を正常に保つ
・脳の働きを補助
・神経伝達物質生成
〈魚介類、レバー、ナッツ、ココアなどに多い〉
マンガン
・骨代謝(骨、靭帯、神経の補強)
・糖脂質代謝(消化吸収する酵素を活性化)
・皮膚代謝などの補助
・下垂体を活性化
・生殖機能低下防止作用(性ホルモンの合成に関与)
・神経伝達物質生成
〈緑茶、紅茶、シナモン、焼きのり、ごまなどに多い〉
クロム
・インスリンの強化(糖や脂質の代謝、血糖値、血圧、コレステロール値を下げる)
〈あおさ、バジル、寒天などに多い〉
ヨウ素
・甲状腺ホルモンを合成(主原料)→成長、基礎代謝の促進
・たんぱく質合成
〈昆布、わかめ、のり、ひじきなどに多い〉
セレン
・活性酸素除去
・甲状腺ホルモンの活性化
〈かつお節、たらこ、辛子などに多い〉
モリブデン(主に肝臓や腎臓に存在)
・尿酸の生成、糖、脂質、鉄の代謝、銅の排泄(他のミネラルとバランスを取りながら体内で機能)
〈大豆製品、レバーなどに多い〉
●コバルト
・ビタミンB12の構成成
・赤血球(ヘモグロビン)の生成、吸収促進
〈しじみなど貝類、サケなど魚類などに多い〉
働きは沢山ありますが、どれも重要な役割を担っているミネラルです。
過剰摂取しても不足しても、書いてある働きが正常に機能しなくなり不調に繋がりますので、栄養を甘く見ず、是非食生活の見直ししてみてください!
美容鍼灸サロン カラダキュアの詳しいご案内はこちらからどうぞ